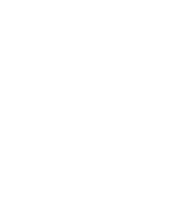ブログ
Hope is not a strategy.
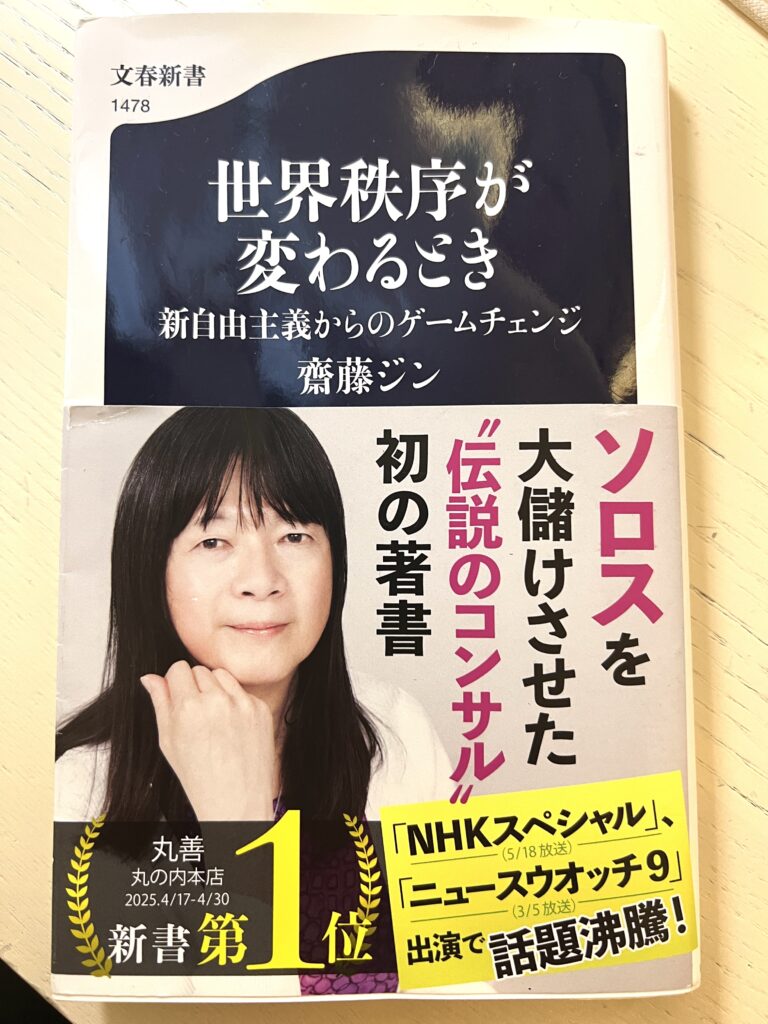
『世界秩序が変わるとき』を読んで考えた。
選ばれる国家、選ばれる企業、その違いはどこにある?
📖 ※本記事はネタバレを含みます。読後の振り返りとしてお読みいただくことをおすすめします。
「難しそうだけど、なんか気になるな」
そんな軽い気持ちで手に取った本が、思いがけず自分のビジネスに直結する気づきをくれた。
斉藤ジンさんの『世界秩序が変わるとき』。
国際政治の話が中心なのに、読み終えたときの印象は、むしろこうだった。
これは、“会社が選ばれる理由”を問い直す本でもある。
そんな風に“自分ごと”として受け取った読書の記録を、ここに残しておきたいと思う。
📖 読書メモ:世界のゲームルールが静かに変わっている
本書で何度も語られていたのは、「秩序が変わる」とは単に戦争や崩壊ではなく、
“ルールが書き換わる”ことであるという事実。
「新しい秩序は、戦争ではなく“ゲームのルールの変更”として訪れる」
世界は今まさに、静かにルールを変えはじめている。
それは、アメリカ主導の新自由主義が揺らぎ、
各国が“自分たちの正義”や“価値観”に基づいて動き出したということ。
これは単なる地政学の話ではなく、
「何が正しいか」ではなく「誰が信頼されるか」で決まる時代が来ているということだ。
🔑 カギとなるキーワード:「コンフィデンス(信認)」
印象的だったのは、「トラスト」ではなく「コンフィデンス」という言葉の使い方。
「信頼される」というだけでは不十分。
「信認される」=“この人(この国)なら、託せる”という存在になる必要がある。
これは、国家に限らず、企業にも、個人にも共通する話だと感じた。
- 実績だけではなく、未来への構想があるか
- 言っていることとやっていることが一致しているか
- 逆風の中でも信じて任せられるか
つまり、**「信認される存在になる準備ができているか?」**が、これからの分かれ目になる。
💡 生産性が低い=まだ“伸びしろ”があるという見方
日本に対する記述も印象的だった。
「日本はこの10年、何をしてきたのか?」
「生産性が低いということは、まだ伸びる余地があるということでもある」
耳が痛くなるようなフレーズだが、同時に励ましにも聞こえた。
たとえば、デジタル化、業務改善、情報発信、仕組み化……
できていないことがたくさんある中小企業だからこそ、
いま、変われば一気に“飛躍の余地”がある。
⚠ Hope is not a strategy.
本書の中で一番刺さったのが、この一言だった。
「Hope is not a strategy.(希望は戦略ではない)」
つまり、
「なんとかなる」「そのうち状況は変わるだろう」といった“願望”にすがるのではなく、
現実を直視し、「ではどうするか?」を決める覚悟が必要だということ。
- 顧客にどう選ばれるか?
- 社会に対してどう価値を出していくか?
- 自社は、どんな“信認”を勝ち得る存在になれるか?
希望より戦略。応援より準備。
このメッセージは、時代の転換期にいるすべての中小企業に響くはずだ。
🧭 読み終えて強く残ったこと
この本は、たしかに国際政治の本ではある。
でも、読み終えたあとに浮かんだのは、
**「これは、経営の話でもある」**という実感だった。
なぜなら、著者が本当に伝えたかったのは、
「この激動の時代に“選ばれる存在”になるための準備とは何か?」という問いだったと思うから。
📌 本書から得た3つのビジネス視点
- “信頼”よりも“信認”される存在へ
→ 商品力や価格以上に、「この人に任せたい」と思わせるかどうかが重要に。 - 生産性の低さ=恥ではなく、可能性
→ できていない部分が多いからこそ、今からでも“化ける”余地がある。 - Hope is not a strategy.
→ 期待や願望よりも、準備と判断が未来を決める。
📚 最後に
大きく変わろうとしている“世界のルール”。
それは遠い国の話ではなく、
私たちの会社、働き方、そして人生の選択にも静かに影響を及ぼしている。
「世界秩序の変化」と「自分の立ち位置」を結びつけて考えたい方へ。
ぜひ一度、じっくり読んでみてほしい一冊です。